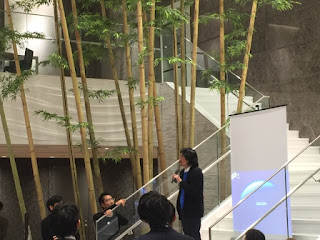実は長崎は高校の修学旅行で行っただけで、30数年ぶりの二度目という事でしたので、軍艦島は初めて行きました。
通称軍艦島と言われる端島炭坑は、正に現在の日本の豊かさを作ってきたと言っても過言ではないと思います。
日本に西洋の技術を持ち込んだグラバー商会が倒産し、隣の高島炭坑の経営を引き継いだ後藤象二郎も大赤字で苦しんだ中、福沢諭吉と大隈重信が岩崎彌太郎に提案し、弟の岩崎彌之助が彌太郎を説得してそれら炭坑を三菱が買取る事となったとの事で、フィクションドラマ?という様なキャスティングです。
その後、炭坑自体もそうですが、三菱、そして日本全体の発展に繋がっていくのですから、その礎とも言える場に立っていると思うと、ゾクゾクとしました。
決してそんな綺麗事ではなく、劣悪な環境の中、過酷な労働を強いられた多くの労働者の犠牲の上での繁栄なのだと思いますが、それでも紹介されていた写真などからは、登っていく、”生命力”の様なものを感じました。
それが、石炭から石油にエネルギーの主役が変わると、繁栄を極めた炭坑が閉山して、廃墟にまで至った光景も、スパンを変えて見れば、人類の栄枯盛衰とも感じられ、色々と考えさせられるのです。
火力から主役を奪った原子力発電は、未曾有の大惨事を起こし、エネルギーの勢力変化は、世界のパワーバランスを変え、その不安定さが一触即発の危機にも繋がっていますが、物資的な豊かさを求めて、一心不乱に働いて来た当時の人達からは、どの様に映るのでしょうか?
決してそんな綺麗事ではなく、劣悪な環境の中、過酷な労働を強いられた多くの労働者の犠牲の上での繁栄なのだと思いますが、それでも紹介されていた写真などからは、登っていく、”生命力”の様なものを感じました。
それが、石炭から石油にエネルギーの主役が変わると、繁栄を極めた炭坑が閉山して、廃墟にまで至った光景も、スパンを変えて見れば、人類の栄枯盛衰とも感じられ、色々と考えさせられるのです。
火力から主役を奪った原子力発電は、未曾有の大惨事を起こし、エネルギーの勢力変化は、世界のパワーバランスを変え、その不安定さが一触即発の危機にも繋がっていますが、物資的な豊かさを求めて、一心不乱に働いて来た当時の人達からは、どの様に映るのでしょうか?
おりしも長崎に向かった4月25日は北朝鮮人民軍の創設記念日との事で、北朝鮮が何らかの行動を取るとの話も流れていましたが、北朝鮮やアメリカのリーダーにも、無人、廃墟となった軍艦島の姿から、欲望の先の愚かさを連想してもらいたいものです。
今回、ハウステンボスにも初めて行きました。
一転、テーマパークの話?って感じですが、こちらも経営面においては、長年赤字続きであった所をHISさんに代わってから、一挙に黒字転換されたのですが、ディズニーランドやUSJの様な華々しい事はできないながらの、ソフトでの仕掛けが見て取れました。
一触即発の世界情勢の中、経営者として自分事としてできる事として、もう資源を争いあって掘り尽くす経営ではなく、無い物から生み出し、アイデアを駆使して、与えられた状況でマネジメント能力を発揮した経営を目指していきたいと思います。
資金も資源も無いので、それしかできないのですが^^;